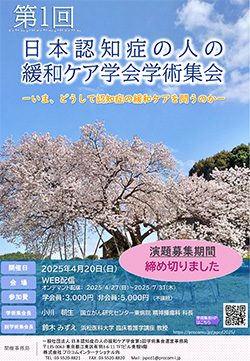日程表・プログラム
日程表
プログラム
学術集会長講演
「いま、どうして、認知症の緩和ケアを問うのか?」
- 座長
- 平原佐斗司(東京ふれあい医療生活協同組合 オレンジほっとクリニック)
- 演者
- 小川朝生(国立研究開発法人がん研究センター東病院精神腫瘍科)
企画担当者より
認知症の緩和ケアの現状と本学会の方向性を考えていきたいと思います。 教育的なセッションのダイジェストとしても活用いただければ幸いです。
特別講演
「認知症になってからも、自分らしく生きるために―当事者の声から学ぶ」
- 座長
- 小川朝生(国立研究開発法人がん研究センター東病院精神腫瘍科)
高山陽子(日本看護協会 看護研修学校)
- 演者
- 藤田和子(一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事)
- インタビュアー
- 小森由美子(認知症介護研究・研修東京センター 客員研究員)
企画担当者より
認知症になってからも自分らしく暮らせる社会を実現したい!
看護師として働いていた45歳のとき、若年性アルツハイマー病と診断された藤田和子さんは、当事者の立場で積極的に発言を続けています。著書では、診断後の「空白の期間」の解消が、これから認知症になる可能性のあるすべての人にとって深刻かつ切実な問題であることを指摘しています。
本講演では、認知症経験専門家として、診断後の課題や自己決定を尊重したケアのあり方を語っていただきます。
聞き手は、認知症介護研究・研修東京センター客員研究員の小森由美子さん。
当事者の声に耳を傾け、新しい認知症観に基づく支援のあり方を考える貴重な機会です。ぜひご参加ください。
シンポジウム
S-1「BPSD、チャレンジング行動」
- 座長
- 遠矢純一郎(桜新町アーバンクリニック)
鶴屋邦江(医療法人実風会 新生病院)
- 演者
- 井上真一郎(新見公立大学 健康科学部 看護学科)
中西三春(東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野)
村島久美子(桜新町アーバンクリニック)
佐藤勝宣(デイサービスすずらん梅丘)
概要
BPSD (challenging behavior)について整理する。
薬物療法については、精神症状緩和という本来の目的と薬理学的鎮静との誤解をとくために、薬物療法の基本から解説する。
非薬物療法については、日本版BPSDケアプログラムの国際共同開発の経緯と実際について紹介する。
企画担当者より
あなたの周りで、未だにBPSDを「問題行動」「迷惑行為」などと言い換えている人はいませんか?例えば、認知症の人が怒りをあらわにしている場合、そこには必ず本人なりの理由があります。それをうまく言葉にできないため、怒りによって周りへ伝えようとしているのです。
近年海外において、BPSDは「チャレンジング行動」と呼ばれており、「認知症の人が困った状況を乗り越えようとしている結果」などとポジティブにとらえる動きが出てきました。そこで本セッションでは、チャレンジング行動と呼ばれるBPSDへのアプローチをテーマとして、薬物療法の基本をご紹介した上で、多職種の視点からBPSDケアプログラムについてわかりやすく解説します。
明日からの臨床にご活用いただければ幸いです!
S-2「新しい認知症観が描く未来―医療安全と穏やかな暮らしで実現する、身体拘束フリーの認知症緩和ケア」
- 座長
- 平岩千代子(最期まで身も心も縛られない暮らし・住まい研究会)
森林朋英(日本看護協会看護研修学校)
鈴木みずえ(浜松医科大学臨床看護学講座)
- 演者
- 長尾能雅(名古屋大学医学部附属病院副院長・患者安全推進部教授)
佐藤(佐久間)りか(認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン 事務局長)
石川容子(医療法人社団 翠会 和光病院)
稲葉一人(いなば法律事務所)
概要
2024年度の診療報酬改定で身体拘束最小化チームの強化が義務図けられたが、現場では、身体拘束の実施の有無に固執しがちである。身体拘束最小化の本来の目的は、認知症ケアの質の向上や認知症の人の尊厳をいかに守るかである。そこで、当事者・安全管理者・法律家・看護師などさまざまな立場のシンポジストからご意見を頂き、認知症の人の尊厳を守るための安全管理と穏やかな生活をめざした身体拘束最小化を考える。
企画担当者より
認知症緩和ケアにおける身体拘束最小化は、新しい認知症観に基づき、尊厳を守り安全で穏やかな暮らしを実現するための基本です。本シンポジウムでは、医療安全の専門家、看護師、弁護士、そして母親が入院時に身体拘束を受けた経験を持つ家族など、多彩な立場のシンポジストが登壇し、現場の実情に即した議論を展開します。身体拘束がもたらす影響、せん妄・転倒への対応、法的リスクの見極めの課題を検証するとともに、2024年度診療報酬改定に伴うチームアプローチの意義と方法を共有します。医療安全と、認知症ケアの質向上による尊厳保持の両立を目指し、具体策を探るこのセッションは、介護・医療関係者のみならず、認知症ケアに関心をお持ちのすべての方に必見です。ぜひご参加ください。
S-3「認知症の軌跡を踏まえた支援(フレイル、身体活動、栄養)」
- 座長
- 森林朋英(日本看護協会看護研修学校)
吉際俊明(医療法人社団慶成会 青梅慶友病院)
- 演者
- 佐藤香苗(東海学園大学健康栄養学部)
後藤響(長崎記念病院リハビリテーション部/長崎大学 医学部保健学科理学療法学専攻)
那須真弓(亀田医療大学)
概要
認知症の人のQOLを維持する上で、認知症がフレイルの一つであることを認識することは重要であるが、どうしても身体的な側面は見逃されがちである。療養のセッティングの違いをこえて切れ目のないケアを考える上で、認知症の軌跡を踏まえた支援を共有することが重要である。認知症の中核症状へのケアだけではなく、身体面を踏まえた包括的な支援について考える。
企画担当者より
認知症の発症から進行に至る過程において、進行段階に応じた個別支援と包括的アプローチを統合することは、認知症の方々のQOL(生活の質)向上にとって重要な要素です。しかし、急性期病院では、主疾患の治療が優先されがちで、栄養管理や基礎疾患の管理といった身体的側面が後回しにされることが少なくありません。本シンポジウムでは、管理栄養士、理学療法士、看護師がシンポジストとして登壇し、実践的な知見を共有します。栄養管理や身体活動を通じて健康を維持し、QOLを高めるためのアプローチについて議論します。
療養の場所を超え、認知症緩和ケアの未来を見据え、認知症ケアに携わるすべての方々にとって、現場で実践できる支援の形を共に探求したいと思います。皆様のご参加を心よりお待ちしています。
S-4「認知症の人とのコミュニケーション~3つの場面から考える~(しゃべり場)企画」
- 座長
- 井上真一郎(新見公立大学 健康科学部 看護学科)
鶴屋邦江(医療法人実風会 新生病院)
桑田美代子(医療法人社団慶成会 青梅慶友病院)
日向園惠(石巻赤十字病院)
立原玲(島根県立中央病院)
佐藤典子(順天堂東京江東高齢者医療センター)
- 演者
- 井上真一郎(新見公立大学 健康科学部 看護学科)
名古屋譲(特定医療法人楽山会 三島病院)
山下いずみ(江別市立病院)
谷向仁(名古屋市立大学大学院看護学研究科)
岡本明大(三重大学医学部附属病院薬剤部)
木野美和子(筑波メディカルセンター)
小川真寛(神戸学院大学総合リハビリテーション学部)
森本景子(地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター)
副島沙彩(国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 精神腫瘍科)
概要
認知症の人の苦痛を緩和するために、私たちは、認知症の人とのコミュニケーションをとるのだが、認知症の人のニーズに沿ったケアになっているか悩むことがある。一人一人の認知症の人の緩和ケアにつながるコミュニケーションについて、3つの場面ごとに、様々な職種の方々の実践を参加者と共有し、明日からの実践に活かすことができればと思う。
企画担当者より
何らかの病気の治療で入院している認知症の人は、様々な苦痛を抱えています。
本企画では、認知症の人の緩和ケアにつながるコミュニケーションについて、以下の3つの場面を取り上げ、演者の皆様にお話しいただきます。
① 苦痛を伴う治療や処置をするときのコミュニケーション
② せん妄を発症している認知症の人のコミュニケーション
③ 意思決定支援の場面でのコミュニケーション
医師・看護師・理学療法士・薬剤師・作業療法士・心理療法士の皆様が、認知症の人のケアニーズをどのようにアセスメントしてコミュニケーションをとっているのか、その実践を共有していただきます。また、参加者の皆さんからの質問やご意見を交えながら、自由に意見交換を行う場としたいと考えています。明日からの実践に役立つヒントを得ていただければ幸いです。
教育コンテンツ
認知症の緩和ケアアプローチとは?(国際的ガイドライン含む)
- 演者
- 小川朝生(国立研究開発法人がん研究センター東病院精神腫瘍科)
末期認知症の人の人工的水分・栄養補給法について
- 演者
- 平原佐斗司(東京ふれあい医療生活協同組合 オレンジほっとクリニック)
急性期入院時のせん妄の予防、評価、対策
- 演者
- 井上真一郎(新見公立大学 健康科学部 看護学科)
日常生活援助における倫理
- 演者
- 吉岡佐知子(松江市立病院)
末期認知症の人への食支援・コンフォートフィーディングオンリー(CFO)
- 演者
- 山田律子(北海道医療大学)
認知症の家族ケアの基本的考え方
- 演者
- 川上千春(聖路加国際大学)
認知症に伴う精神症状(総論)
- 演者
- 内田直樹(医療法人すずらん会たろうクリニック)
身体拘束最小化のマネジメント
- 演者
- 日向園惠(石巻赤十字病院)
身体拘束とは
基本的な考え方、世界の動向、我が国の政策動向
- 演者
- 平岩千代子(最期まで身も心も縛られない暮らし・住まい研究会)
行動心理症状 (BPSD)へのアプローチの基本
- 演者
- 野澤宗央(桜新町アーバンクリニック)
パーソンセンタードケアと認知症の緩和ケア
- 演者
- 鈴木みずえ(浜松医科大学臨床看護学講座)
タイムスケジュール、演者は決まり次第、更新いたします。